饅頭こわい
No.183
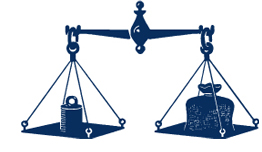 妙な題名だが、落語好きなお方はお気づきだろう。
妙な題名だが、落語好きなお方はお気づきだろう。
これは江戸時代の中頃に成立した演目で、若い落語家たちが高座にかける前座話として受け継がれてきた作品である。暇な町内の若い者が集まって、それぞれの好物を話し合った後、今度は怖いものは何かとなったとき、皆が蛇や蜘蛛(クモ)、嫁さんなどと言うなか、一人の男が「饅頭がこわい」と震えた。それはおもしろいとして、若い者連中が饅頭を買ってきて、その男に投げつける。怖がって騒ぐか、気を失うかと、どんな反応するか楽しみにしていると、「怖いものを目の前から消す」として、饅頭を全部食べてしまう。
要は、その男はただで好物を思う存分楽しみ、若い者は騙されたというオチのものであり、落語の題材になるほど、江戸時代も砂糖が使われていた。
以前から、江戸時代は砂糖が高価で庶民の口には入らないと言われてきたが、昨今そうではなかったとわかってきた。生類憐れみの令で有名な五代将軍徳川綱吉の治世の初期の記録だと、砂糖百斤(およそ六十キログラム)で銀百五十匁(銀は相場で左右したが、幕府は一応、一両小判一枚を銀六十匁としていた。百五十匁は二両半ほど)内外だったとある。もっともその後、長崎での交易を監督する長崎会所ができたことで砂糖には二百%から三百%という関税がかけられたため、百斤で銀六百六十匁(十一両)にまで高騰した。ちなみに金一両あれば、町民一家が一カ月生活できたとあるので、一両は二十万円くらいと考えてよいかと思う。
たしかに今から思えば高価でとても買えないが、しっかりと抜け道はあった。もともと砂糖は南蛮船や清船が船のバラスト代わりに積んできたもので、元値はただに等しい。また白砂糖だからこそ、贈答品や高級品として通用するのであり、航海中に潮を浴びたものや変色したものは値打ちがないものとして、長崎会所を通じず、出島に出入りする者に捨て値で売られていた。この捨て値の砂糖が、庶民の甘味のもとになった。
とはいえ、輸送費はかかる。長崎ではただのような値段でも、江戸まで運べばそれなりの値段になる。つまり、長崎と江戸では砂糖の価値に差があった。青森公立大学の長岡朋人准教授の研究※によると、江戸時代、九州の子供は江戸の子供より虫歯が多かったとされている。
砂糖は脳の活動を助けるという効果もあるが、摂取しすぎるとう蝕、糖尿病などの原因になる。江戸時代より容易に砂糖が手に入る現代、その功罪を歯科医師としてどう扱うか、悩ましい限りである。
※)2016年10月5日の読売新聞に研究内容の一端が紹介されている。


